.
~4小節(くらい)ずつ作るオリジナルソング~
【第3回】
聞かせどころ「サビ」を作るぞ!
(01/09/28)

ケケ中
|
オンラインソフトで作ったオリジナルソングを全世界に発信しよう! というちょっと大げさなこの企画。ちょっとおマヌケな歌手志望の青年「ケケ中」は果たしてデビューできるのか? それはすべてプロデューサーであるモッティの手腕というか力量というかきまぐれにかかっているのだ!!
今回は、オリジナルソングの聞かせどころ、「サビ」を作るぞ。4小節(くらい)ずつ、ゆっくりアバウトに作ってみよう!
|

モッティ
|
 耳に残るメロディを作れ!
耳に残るメロディを作れ!
ある日、何を間違ったか窓の杜編集部にふらりとやってきてしまった東大阪出身の歌手志望の青年、ケケ中は、ワタクシことネタに詰まったライターのモッティに言いくるめられて、本連載の実験台……じゃなくてモデルとなり、オンラインソフトでオリジナルソングを作って歌手デビューを目指すことになってしまった。彼に与えられた名前は「ケケ中正義」。前回はオリジナルソングの曲調である「ちょっとトロピカルなフュージョンっぽい歌謡曲」に向いた16ビートのリズムを作ってみた。
さて、ケケ中はというと、歩く姿を見ても心なしか16ビートを刻んでいるようになってきた。イスに座っても手で机をツクツクタクツクと叩いている。まぁ、はたから見たら単なる貧乏ゆすりそのものなのだが。これも、ケケ中が自ら持ってきたCDやMDを没収し、前回作ったリズムパターンを四六時中聞かせ続けたおかげというものだ。
リズムの次は、いきなりメロディ、それも曲の聞かせどころである「サビ」から作ることにする。曲を作るときにはイントロ、Aメロ、Bメロ……みたいに頭から順に作っていってもいいのだが、ふと頭に浮かんだメロディを基に曲全体のイメージを広げていく、という方法もアリだ。というか、そっちの方が作りやすい場合が多い。ケケ中もリズムが体に染み付いてきたみたいだから、何かメロディが浮かんでいるかもしれない!
ということで、リズムを刻みつづけるケケ中が何か鼻歌でも歌っていないかどうか、それとなく耳を傾けてみた。案の定ケケ中は机を叩きながら何か言っているようだ。
| ケケ中: |
「はぁツクツクタクツク・ツクツクタクツク・はぁツクツク」 |
モッティは軽いめまいを覚えた。ちょっと期待しすぎたようだ。頭を切り替えて、ケケ中に切り出す。
| モッティ: |
「おーい、メロディを作るんだけど、何かいいメロディは浮かんだ?」 |
| ケケ中: |
「え? わしが考えるんでっか? モッティさんプロデューサーでっしゃろ? そんくらいやってくれてもええやん」 |
| モッティ: |
「どんどん図々しくなってきたな。それに言葉が大阪弁丸出しになってきたし」 |
| ケケ中: |
「まかせろ言うたのはモッティさんやないですか。それともわしの美声をそんなに聞きたいんでっか?」 |
| モッティ: |
「お、そうだ。まだケケ中の歌を聞いていなかったな。メロディ云々はその後にしよう」 |
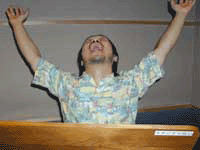 |
| ケケ中の歌声、それはジャ○アンリサイタル…… |
勢い込んで歌い始めるケケ中。その結果は……。ひとことで言うと、「ジャ○アンリサイタル」。詳しいことはモッティの表情が物語っているだろう。しかたない。ケケ中の音楽的センスはあきらめ、オリジナルソングの作曲はモッティがすべて受け持つことにしよう。
 「ソング頼太」で鼻歌からMIDIに変換!
「ソング頼太」で鼻歌からMIDIに変換!
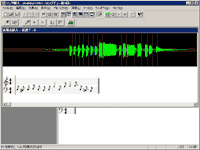 |
| 「ソング頼太」の「鼻歌の鉄人」機能でMIDIを音声入力! |
ここでギターを取り出したりピアノの前に向かってもいいのだが、頭に浮かんだメロディをさっと音に出せる楽器、それは声だ。今回は声を使ってそれをMIDIの音楽信号にしてみる。この分野の定番は「ソング頼太」。「鼻歌の鉄人」という機能が音声入力による作曲を手助けしてくれるぞ。まずはPCにマイクを接続して、音が鳴るかどうかチェックしておこう。
「ソング頼太」の環境設定はカンタン。[演奏]-[MIDIデバイス]で「MIDI Mapper」を指定し、[ツール]-[WAVデバイス]で「WAV入力デバイス」と「WAV出力デバイス」の両方に「Wave Mapper」を指定すれば、通常は問題ないはずだ。次に[プロジェクト]-[新規作成]でプロジェクト名を付けてプロジェクトを作成したら、[プロジェクト]-[編集]で「テンポ」に「92」を入れておく。これは前回リズムを作ったときに決めたテンポだ。続いて[ファイル]-[新規作成]で、SRT形式のメロディのファイルを用意する。ここでも同様に「テンポ」は「92」にしておく。
これで鼻歌入力の準備は整った。[ツール]-[鼻歌の鉄人]を選び、ツールバーにあるマイクのアイコンをクリックすると音声入力の開始だ。音声入力のときには「んー、んー、んー」という鼻歌をマイクに近づけて歌うのがコツ。音と音の切れ目を意識して歌おう。息や鼻息が入るとうまく認識してくれないぞ。こんな風に歌ったというサンプルWAVファイル「hanauta.wav」を用意したのでダウンロードして参考にしてほしい。で、うまく認識されると鼻歌がリアルタイムに音符になって表示される。ここまで認識されるまでには十数回かかったが、コツを覚えてしまえばこちらのものだ。試聴してみて、だいたい思い通りになっていたら、トラックのアイコンをクリック。これで鼻歌を採譜したデータが、メロディファイルのデータに転送される。メロディファイルは適当な名前を付けて保存しておこう。
このメロディファイルをMIDIに変換するには、[プロジェクト]-[編集]の「メンバーファイル」の「Track 1」にメロディファイルを指定する。続いて[プロジェクト]-[MIDIファイル作成]を行うと、プロジェクトファイルの名前と同じMIDIファイルが作成される。「MIDIファイル作成」ダイアログボックスの各項目は、初期設定のとおりで問題ない。このMIDIファイルも「hanauta.mid」として用意しておいた。聞いてみてほしい。
 メロディをリズム、コード、ベースに乗せる!
メロディをリズム、コード、ベースに乗せる!
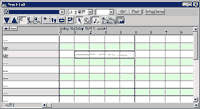 |
| トラックリストウィンドウで、メロディのトラックをコピー |
なんとかサビのメロディをMIDIにすることができたが、これだけではどんな感じの曲なのかがよくわからない。モッティの頭の中で聞こえている音楽をケケ中に伝えるためには、仮の伴奏をつけておく必要があるのだ。具体的には、リズムとコード(和音)、ベース(低音)をメロディと統合するのだ。
そこで、前回に続き「Cherry」の出番となる。「hanauta.mid」を読み込んで、メロディのデータを整えるところから始めよう。このサビの部分は、実はいちばん初めに8分休符が入ることを考えて作ったものだ。だから、メロディのデータが入っているトラック#2のすべてのデータを8分休符の長さ分、つまり半拍後方へとズラそう。トラックウィンドウ左上のプルダウンメニューから「Track#2[]」を選んだら、ウィンドウ右半分に表示されているメロディデータを矢印ツールですべて選び、半拍分ドラッグするのだ。続いてそれぞれの音のタイミングや長さをトラックウィンドウの鉛筆ツールで調整する。メロディを調整したら、いったんセーブしておこう。
セーブ後、トラックリストウィンドウに移動し、トラック#2の赤い点線のように見える部分をマウスで選択したら、右クリック-[コピー]を行う。これを前回作った「rhythm01.mid」と統合しよう。「rhythm01.mid」を開いたら、トラックリストウィンドウのトラック#2の1小節目を右クリック-[貼り付け]だ。これで、リズムの上にメロディを乗せる作業は完了だ。
続いて、コードとベース音を入力する。トラックリストで、上から4番目のトラック#3の列を右クリックして[プロパティ]を選択する。「Port」に「A」を、「CH#」に「02」を設定。同じようにトラック#4にも「Port」に「A」を、「CH#」に「03」を設定しておこう。トラック#3にコード、トラック#4にベース音を入れていく。
次に、トラックウィンドウ左上のプルダウンメニューで「#3」を選んだら、楽器音を選択するために[挿入]-[プログラムチェンジ]を選択しよう。ウィンドウ左側に挿入された「Program」という項目の文字部分をダブルクリックすると、楽器音の選択ダイアログが開く。真ん中の「PC#」に表示された楽器音からコードの音に合ったものを選ぶ。ここでは「006 El.Piano 2」を選んでみた。トラック#4にも「035 Pick Bass」の楽器音を設定しておこう。あとは、ピアノロールインターフェイスで鉛筆ツールを使いながら音を入れていけばOKだ。仮の伴奏だからコードもベースも全音符、いわゆる「白玉」で「ジャーン」と鳴らすだけでいいだろう。
ここで、コードのことについてちょっと解説しておこう。このメロディのキー(調子)はハ長調(Cメジャー)で作ってある。「フツーのドレミファソラシド」で考えてOKだ。この「フツーのドレミ」の「ド」の音を英語で「C」というのは知ってるかな? 「ラ」が「A」で「ソ」が「G」にあたる。コードの名前(コードネーム)を指すときには通常英語の名前を使って表す。いちばん基本的な長調の和音では、元になる音(基音)の上に2全音(4半音)上の音、さらに1音半(3半音)上の音が重なる形になっている。「ド・ミ・ソ」の和音がこういう形だ。そこで、この和音のことを基音の音をとって「C(Cメジャー)」という名前で呼んでいる。これにしたがって「ソ」の音、つまり「G」音を基音とした「ソ・シ・レ」という和音は「G(Gメジャー)」と呼ぶ。ベースは基音を鳴らすことが多い。
ちなみに2番目の音が半音下がっていれば短調の和音になり、「ド・ミのフラット・ソ」というコードは「Cm(Cマイナー)」と呼ぶ。
ハ長調の曲の場合、C、G、Am、F、Dmなどのコードがよく使われる。このメロディには「C-G-Am-F」というコード進行がぴったりあてはまる。ベース音もコードネームのとおり「ド-ソ-ラ-ファ」にしておいた。ここまでのMIDIファイルは「olsdebut-03-01.mid」だ。メロディだけだとあいまいだった曲の感じが、ほんのちょっとだけつかめるはずだ。
 コードとベースにもっと頭をひねれ!
コードとベースにもっと頭をひねれ!
よし、これをケケ中に聞かせよう! と意気込むモッティの背後に人の気配がした。「モッティ、手を抜きすぎじゃないか?」……フランクン古田先輩だ。
| モッティ: |
「古田さん! いつ来たんですか?」 |
| 古田: |
「いつ来たかなどどうでもいい。それよりもモッティ、いくら仮の伴奏だといっても、もうちょっとコードとベースの関係を考えろ。『母が子を負う、自然の摂理なり』というではないか」 |
| モッティ: |
「高見山が出てた『一日一善、お母さんを大切にしよう』ってCMですか?」 |
| 古田: |
「とーじまりよーじんひのよーじん……ってそんなCM、若い者は知らないぞ。そうではなくて分数コードを使ってカッチョイイ曲を作るのだ」 |
| モッティ: |
「分数コード。G on BとかD on F#とかっていうアレですか?」 |
| 古田: |
「そう。コードの基音、つまりCだったらド、Amだったらラなどの音の代わりに、それ以外の音をベースに弾かせるというヤツだ」 |
| モッティ: |
「この場合だったらどうするんですか?」 |
| 古田: |
「1小節目から4小節目までの流れを考えるのだ。2小節目でベース音がドからソへと飛んでいるな。ここをシにするだけで、ド-シ-ラ-ファとベース音が上から下へと流れるようになるだろう」 |
とりあえずMIDIファイルを直してみる。確かにベース音がバタバタしなくなって、流れがわかるようになった。
| モッティ: |
「ほう、シはGコードの構成音ですから変な響きにはなりませんね」 |
| 古田: |
「そうだ。母、つまりベース音で流れを作り、その上に子であるコードを乗せるのだ。ついでにいえば、2小節目はG on Bではなく構成音の近いEm7 on Bにした方が複雑な響きになるぞ」 |
| モッティ: |
「代理コードってやつですね」 |
| 古田: |
「うむ。ついでのついでに3小節目と4小節目のAとFの間にGを入れると、コード進行としては美しいぞ」 |
| モッティ: |
「あ、リズムのアクセントといっしょに入れるとかっこよさそうです」 |
| 古田: |
「それだけわかればよい。もう行かなければ……ここのコーヒーはもらっておくぞ」 |
| モッティ: |
「あ、それ灰皿ですよ」 |
| 古田: |
「くゎ、もう遅いわ」 |
 |
| いや、そんなに目を見開かれましても…… |
灰皿となっている缶をくわえながら古田さんは去っていった。「分からないことがあったらメールしろ」って言ってるくせに、先回りしてくるんだよなぁ。まぁ、それはおいといて、助言をもらった点を修正したMIDIファイルが「olsdebut-03-02.mid」だ。どんな風に変わったか聞いてみてほしい。
さて、ケケ中のMP3プレイヤーにこのサビの部分もこっそり入れておいたし、次はイントロでも作ってみようか。こんな調子で果たしてケケ中はデビューできるのか!? 注目せよ!!
 今回使用したオンラインソフト
今回使用したオンラインソフト
(文:モッティ 監修:フランクン古田)
記事中の楽曲制作者は望月 貞敏氏です。著作権は同氏に帰属しますので、こちらのファイルの無断転用・転載は著作権法違反となります。


 トップページへ
トップページへ キミはオンラインソフトでデビューできるか!? INDEX
キミはオンラインソフトでデビューできるか!? INDEX