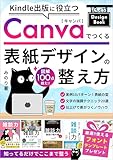石田賀津男の『酒の肴にPCゲーム』
ゲーミングPCは光る方がコスパがいいらしい
2025年5月15日 16:45
光るやつがゲーミングPC
以前、『ゲーミングPCとは何か?』という定義論の話をしたところ、『LEDがピカピカ光っているやつ』という身も蓋もないご意見をいただいた。そう、本当にそのとおり。あんなにピカピカ光るPCはゲーミングPCしかない。光るPCはゲーミングPCだ。正解。
ゲーミングPCはあくまで道具であり、光る必要はないと思っている方もいらっしゃると思う。ところが現在、装飾用LEDを搭載しないPCパーツを集めてPCを組もうとすると、これが案外難しい。
ゲーミングPCに必須のビデオカードはほとんどがLEDを搭載しているし、CPUクーラーやケースファンもLED搭載のものが多い。何より、PCケースのサイドパネルがガラスやアクリルによる透明な素材を採用したものが非常に多く、光り輝くデコPCを作ってくださいと言わんばかりの状態だ。
なぜこんな状況になっているのか、考察と解説をしていこうと思う。
デコレーションPCの歴史と変遷
光るゲーミングPCの始祖が何かというのは、筆者も確たる答えは持っていない。知っている範囲だと、1990年代から欧米で流行りだしたLANパーティがきっかけだと思っている。PCを持ち寄ってLAN環境で遊ぶというイベントの特性から、自分のPCを他人に見せるという意図が生まれた。また大規模なLANパーティでは、自分のPCを目立たせておくと場所がわかりやすいという狙いもあったとか。
その後、Alienwareが既製品の光るゲーミングPCを発売。同ブランドが持つ未来的なイメージを植え付けるとともに、高性能なゲーミングPCが光るというイメージを業界に定着させた。これにPCメーカー各社が追従し、一時はあらゆるゲーミングPCが光る勢いだった。今は下火になっているが、その当時のイメージから『ゲーミングPCは光る』というイメージがついたのだと思う。
これと並行して、PCパーツ単位でLEDを搭載する製品が増加。今やあらゆるパーツにLED搭載モデルが用意されているうえ、PCケースは内部が見えるクリアパネルを採用したものが増えたことで、多彩なLEDデコレーションが可能になった。SNSの普及により、他人にPCを見せやすくなったことも影響していそうだ。
ちなみにLEDによるデコレーションが流行する前には、水冷パーツで魅せるPCを自作する方々が活躍していた。ビビッドなカラーの冷却液を通したチューブを内部に張り巡らせたPCは、未来的なデザインでありつつ、性能面でのメリットもあった。コストと技術の面で難度が高かったが、PCの中を見せるという意味ではこちらが先駆けと言えるかもしれない。
LEDを内蔵した方が安上がりになる
かくして現在はあらゆるPCパーツが光る時代になり、光らないPCパーツが見当たらないことすらある。筆者は長年にわたってゲーミングPCを見てきて、光らせ方に趣向を凝らしたPCを見るのも好きだ。ただ自分で使うとなると、PCは足元に置いてあって見えないし、静音性や冷却性能の方を重視するので、何ら光る必要はない。
となれば、光らないPCやパーツを選びたくなる。見ないものを光らせておくのは無駄に電気を食うだけだし、LEDを取り除いてくれた分だけ価格も下がってくれていいはずだ。
この答えは、PCメーカーが時折、愚痴をこぼすように語っているのを見かける。例えばこちら。
まったく光らないのが全く売れないと言えば答えがでるかな。#ASR質箱 ←過去ポストまとめハッシュタグ
— ASRock Japan (@AsrockJ)May 13, 2025
・ASRock Japan公式Youtubeチャンネルで詳細解説もしてます。よかっ...
続き→https://t.co/EThvKCuM07#マシュマロを投げ合おう
この一文がすべてを物語っているのだが、もう少しわかりやすく情報を補足しよう。
メーカー側が商品の売れ行きを見ると、LEDを搭載しない製品より、搭載した製品の方がよく売れるというデータがあるという。ユーザー目線だと意外に感じるかもしれないが、実際にメーカーの販売データがそうなのだから、今はそういう時代なのだと言うしかない。
そうなると、光らないPCパーツは作られなくなっていく。少ないニーズがあるとしても、光るか光らないかだけの違いで別モデルを用意し、2つの製品をラインナップするのは、メーカーにとっては負担になる。しかも、どちらか一方が品切れとなった時の生産調整も手間がかかる。光る1モデルに絞れば、手間も負担もなくなる。
ではLEDの部品が減る分、価格も下げられるのかというと、これもそう簡単にはいかない。LED搭載モデルが主流となった今、LED非搭載の製品は小ロットのスペシャルモデルになる。あえてLED非搭載の製品を作ると、逆に価格が上がってしまうため、LED搭載モデルに絞って大量生産した方が安く上がるのである。
『価格が上がっても構わないから、光らないモデルを作ってくれ!』という方は、そう多くないだろう。LED搭載モデルは大抵、設定変更でLEDを消灯できる。最近はPCに搭載されるすべてのLEDを統合制御できるソフトウェアも用意されており、不要な時には全部消灯という設定も簡単にできるようになっている。
PCを光らせる意義は大きい
筆者のように、PCパーツが光らなくていいという方は一定数いるのは確か。ただPCパーツが光るメリットは見た目だけでなく、取り付けた際にLEDが光ることで、とりあえず通電できたことが確認できる。通電できても不具合がないとは限らないが、トラブルの原因の切り分けはしやすくなる。自作に不慣れな方ほど取り付けミスが起こりやすいので、LEDの存在はより有益だ。
PCケースのサイドパネルの透明化に関しては、当初は冷却性能に劣るとして避けられたこともあるが、現在は設計が改善されてあまり問題視されなくなった。また強化ガラスやアクリルを採用するためのコストも下がり、価格面でのデメリットもなくなった。そうなればデザイン的に優れ、人目を引くケースの方が売れる。メーカーとしてもアピールしやすいというマーケティング的な意味もある。
現在のLEDデコレーションPCブームがいつまで続くかはわからないし、いつかは光らないPCパーツが主流になる時代に戻ってくるのかもしれない。筆者の予想では、おそらく戻ることはなく、もっと自由度が高まっていくのだろうと思っている。
ただ、ゲーミングPCが光る意味はある。光るPCと光らないPCを我が家の8歳男児に見せたら、光る方がいいと言うに決まっている。ゲーミングPCや自作PCに興味を持ってもらい、すそ野を広げるという意味で、光ることは有意義だ。
PCの魅力を十分にわかっていて、光る必要がないと思っている方は、LEDを消灯して使おう。それだけのことだ。
1977年生まれ、滋賀県出身
ゲーム専門誌『GAME Watch』(インプレス)の記者を経てフリージャーナリスト。ゲーム等のエンターテイメントと、PC・スマホ・ネットワーク等のIT系にまたがる分野を中心に幅広く執筆中。1990年代からのオンラインゲーマー。窓の杜では連載『初月100円! オススメGame Pass作品』、『週末ゲーム』などを執筆。
・著者Webサイト:https://ougi.net/
PCゲームに関する話題を、窓の杜らしくソフトウェアと絡め、コラム形式でお届けする連載「石田賀津男の『酒の肴にPCゲーム』」。PCゲームファンはもちろん、普段ゲームを遊ばない方も歓迎の気楽な読み物です。

















![【Amazon.co.jp限定】1冊ですべて身につくHTML & CSSとWebデザイン入門講座[第2版] (特典:「Webデザイナーのポートフォリオの作り方入門講座」データ配信) 製品画像:2位](https://m.media-amazon.com/images/I/51skMJ-OVcL._SL160_.jpg)