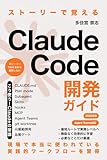働く人のための「DaVinci Resolve」
第3回
無料の「DaVinci Resolve」で編集作業を開始! 撮影した素材の取り込みと整理
撮影した動画と音声を[メディアプール]に読み込み、ファストレビューする
2023年4月27日 13:54
本連載では、無料で使える高機能な動画編集ツール「DaVinci Resolve」の使い方をお伝えしています。
仕事のために動画を自分で作る羽目になった人に捧ぐ「DaVinci Resolve」講座3回目です。4月17日に「DaVinci Resolve 18.5」のパブリックベータが公開されました。およそ1年ぶりの大型アップデートになりますが、AIによる音声認識や[カット]ページの機能強化などが図られています。
ただ現時点では新機能がまだ英語メニューだったり、音声認識も英語だけだったりと、正式版になるまでにはまだ数回のアップデートが出ると思われます。正式版が出た段回で本連載でもv18.5を使用する予定ですが、まだしばらくは正式版の最終バージョンであるv18.1.4を使用していきます。
さてこれからしばらくの間、講座で使用する素材を用意しました。社内向けビデマニュアルを作るという想定で、編集部の長谷川さんに、インプレス社内にあるコーヒーメーカーの使い方を教えて貰うという動画素材を、インプレスの動画チームにお願いして撮影してもらいました。筆者は撮影に立ち会っていません。
社内マニュアル等を作る場合、最初は自分1人で撮影から編集まで行なうことになるかもしれませんが、事業として回るようになれば、撮影を他の人に依頼するというケースも出てきます。テレビ放送などの場合、撮影者と編集者はそれぞれが専門職ですので、編集者が撮影の現場に行くということはありません。撮影された素材を見て、最適な解を見つけ出すのが編集者の役割です。
今回からは、撮影した素材のことを何も知らないという想定で、レッスンを進めていきます。
プロジェクト設定の初期値を設定する
作業開始のたびに行なうのが、新規プロジェクトの作成です。
- 「DaVinci Resolve」を起動し、画面右下にある「家」のアイコンをクリックして、[プロジェクトマネージャ]を起動します。
- 右下の[新規プロジェクト]ボタンをクリックして、新しいプロジェクトを作成します。名前は「コーヒーメーカー1」にしておきます。
何もない空っぽのプロジェクトが作成されました。ここで、今後の作業が楽になるよう、プロジェクトの設定を確認しておきます。
- [ファイル]メニューから[プロジェクト設定...]を選択すると、[マスター設定]が開きます。最初にタイムライン解像度とフレームレートを設定しておきます。今回は社内のサーバにHD解像度でアップロードして共有するという想定にします。
- タイムライン解像度を[1920×1080 HD]に設定します。続いてタイムラインフレームレートを[29.97]に設定します。連動して[再生フレームレート]とビデオモニタリング内のビデオフォーマットが変更されます。
フレームレートは、1秒間に何コマの映像を再生するかの設定になります。今回撮影してもらった素材のフレームレートが29.97でしたので、このコマ数で設定しています。本来はここで設定する前に、素材動画のフレームレートを調べておく必要があります。ここで設定した解像度とフレームレートが、このプロジェクト内で新規に作成するタイムラインのデフォルト解像度とフレームレートになります。
プロジェクト設定の画面を下にスクロールすると、[作業フォルダー]というエリアが出てきます。ここにはプロキシ、キャッシュファイル、ギャラリースチルの保存場所を設定します。これらのファイルは、「DaVinci Resolve」の中から参照しますが、直接フォルダー内を探して参照する機会はありませんので、前回の環境設定で指定したバックアップの保存場所と同じでかまいません。
もう1カ所、パスを確認する場所があります。右サイドバーの[キャプチャー・再生]をクリックし、真ん中あたりにある[キャプチャー]エリアの[クリップの保存先]を確認してください。ここも先ほどと同じ場所を指定しておきます。
これらの保存場所は、「DaVinci Resolve」を起動するたびに毎回チェックされますので、取り外す可能性がある外付けSSDなどを指定しないでください。この設定をプリセット化して毎回使用したい場合は、画面右上の[…]をクリックして、[Set Current Settings as Default Preset...]をクリックします。
確認のダイアログが出ますので[更新]をクリックし、プリセット名に名前を付けて保存しておきます。以降は新規プロジェクトを作るたびに、この設定が自動的にセットされますが、別の設定にしてしまってもすぐにいつもの設定に戻すことができます。ここまでできたら、右下の[保存]ボタンをクリックして、プロジェクト設定を保存します。
素材をロードして中身を確認する
これからしばらくは[カット]ページで作業を行ないます。画面の一番下で、[カット]をクリックし、[カット]ページに移動しておきます。[メディアプール]に素材を読み込みます。
- [メディアプール]のエリアで右クリックし、[メディアの読み込み...]を選択します。
- 今回の作業で使用する素材をすべて選択し、[開く]ボタンをクリックします。
[メディアプール]に素材が読み込まれました。動画素材と、音声素材があります。編集を始める前に、どのような素材があるか、一通り中身に目を通しておくことは重要です。せっかく撮影したのに、気がつかなくて使われないといった、もったいないミスを防ぐためです。
では読み込んだ素材は、どういう順番で見ていくべきでしょうか。今回の素材はシーンごとにファイル名が付けてありますので、名前でソートするのが良さそうです。そこで、[メディアプール]上部にある[メディアの並び替え]ボタンをクリックして、[クリップ名]を選択します。
クリップ名の順に並び替えが行われました。今回のようにファイル名で区別していない場合でも、ほとんどのカメラは独自の名前の後ろに撮影順に番号を振っていくので、クリップ名で並べることで、撮影したカメラごとの撮影順を把握できます。また同じシーンを撮ったテイクがいくつあるかも、同時に把握できます。
[カット]ページには、素材を素早く把握するための[ファストレビュー]という機能があります。
- 画面上部中央にあるアイコンから、[ソーステープ]を選択します。ビューワーが変化し、すべての素材が1本のテープに記録されているような状態で表示されます。
- ビューワー下のアイコンから、[ファストレビュー]をクリックします。
すべての素材が順番に再生されます。再生されない場合は、スペースキーを押してください。スペースキーを押すたびに、再生と停止が切り替わります。
長いクリップは早回しで、短いクリップはそのままの速度で再生されます。だいたい1つのクリップが5秒程度で再生されるよう、速度が自動的に調整されます。全体の素材を見ると、各シーンに分けて、撮影サイズを変えて同じ事を何度か行なっているということが把握できました。これらを組み合わせて編集すればいいんだな、という事がわかります。
音声のみのファイルは個別にクリックして再生します。シーンごとに動画と同じ音声が収録されていますが、動画のほうは音が遠いのでカメラマイクで集音したもの、音声ファイルは胸に付けたラベリアマイクの音を集音したものということがわかります。
つまり編集時には、映像ファイルと音声ファイルを合体させた状態で行なっていく必要があります。次回はこのような、映像と音声を別々に収録した素材に便利な機能をご紹介します。















![【Amazon.co.jp限定】1冊ですべて身につくHTML & CSSとWebデザイン入門講座[第2版] (特典:「Webデザイナーのポートフォリオの作り方入門講座」データ配信) 製品画像:2位](https://m.media-amazon.com/images/I/51skMJ-OVcL._SL160_.jpg)