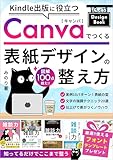ニュース
“風呂キャンセル”を防ぐアプリと「デジタル暗記ノートアプリ」が中高生によるモバイルアプリコンテストで金賞
東京都開催の「モバイルアプリコンテスト2024」
2025年2月7日 12:40
東京都教育委員会は、中高生が自分で開発したモバイルアプリを表彰する「モバイルアプリコンテスト2024」を開催し、その結果発表と表彰式を1月19日に開催した。
モバイルアプリコンテストは、IT人材を育成する「みんなでアプリ作ろうキャンペーン」の一環として東京都教育委員会により毎年開催されている。今回は、2024年8月~11月の募集期間に作品を企画書と説明動画とともに応募。12月の審査を経て、11作品が金賞・銀賞・銅賞として表彰。
応募テーマは「世の中の問題を解決するモバイルアプリ」。前回の倍以上である70以上の応募があったという。表彰式では、審査員や受賞者から口々に「前回よりもさらに全体のレベルが上がった」との声が上がっていた。
なお前回の「モバイルアプリコンテスト2023」は都内の国公私立高校の生徒が対象で、一部、都立の中高一貫校の生徒の参加もあったが、今回は正式に中学校の生徒も対象になった。
表彰式には小池百合子都知事もビデオメッセージで登場。「私たちの身のまわりでデジタル技術が日進月歩で発達している。たとえば生成AIは瞬く間に高い性能を発揮するようになった。そうしたテクノロジーを若い皆さんが使いこなすために、東京都はこのモバイルアプリコンテストを実施している。自分で作ったアプリで課題を解決しようという皆さんの意欲を心強く思う。いつか皆さんが最先端の技術を駆使して、東京だけでなく日本や世界を舞台にイノベーションを起こし活躍することを期待している」とあいさつした。
表彰後には、審査委員長の株式会社インプレス 窓の杜編集長 鈴木光太郎氏が総評を行った。去年よりさらに応募者全員のレベルが上がっているとして、「着眼点、技術力、UI、デザイン、プレゼンテーションなど全部のレベルが高くなっている」と語った。それができた理由の一つとして、おそらく開発にAIを活用しているのではないかと推測し、また皆が身近な課題からアプリを作っていることをふまえ、皆が自分の必要なアプリを作れてしまう時代になってそれを実践していることがすばらしいと講評。「『ないものは作る』を皆さんができているのがすばらしい」とまとめた。
金賞2作品
金賞には2作品が選ばれた。
デジタル暗記ノートアプリ「Nanoha」
金賞の1作品目としては、中野区立中野中学校の中村承太郎さんによる「Nanoha」が選ばれた。
「Nanoha」は、重要語句に緑マーカーを引いたノートに暗記のために重ねる赤シートのデジタル版といえる、デジタル暗記ノートアプリだ。
従来のノートでは整理整頓できていないと探すのに時間がかかるのを、デジタルのノートで解決する。さらに、既存のノートをスキャンしてデジタル化する機能や、AIにより暗記ノートを生成する機能、ノートからのクイズ作成機能も備える。
審査員からは、学生にとって身近な暗記をテーマにしていることや、スキャンやノート自動生成やクイズなど使ったときに便利なように作られていること、ヘルプ画面なども作り込まれていて使いやすくなるよう工夫されていることなどが、選考理由として語られた。
中村さんは受賞コメントで、「大変光栄」と述べ、いま生成AIについていくつかアイデアがあるので、高校受験を乗り切ったら実現したいと語った。
表彰式後の記者会見によると、中村さんは小学校高学年でプログラミングを始めて、中学生になってからテキストによるプログラミングを始め(現在中学三年生)、趣味として毎日プログラミングしているという。今回の受賞作のアイデアは中学一年生のときからのもので、コンテスト応募に向けて5か月ほどで作ったとのことだった。
“風呂キャンセル”を防ぐ「Fulove(ふろ~ぶ)」
金賞の2作品目としては、東京都立南多摩中等教育学校の吉田祐梨さんによる「Fulove(ふろ~ぶ)」が選ばれた。
疲れて帰宅したあと面倒なので入浴しないでいてそのまま寝てしまう“風呂キャンセル(風呂キャン)”の問題について、風呂キャンが友達にバレるぐらいなら入浴するという心理をもとに、入浴した記録を友達と共有するというもの。シャワー音検知による不正防止や、ユーザー認証、風呂に入らないとアイコンが薄汚くなるなど、作り込みもなされている。
審査員からは、着眼点の圧倒的なユニークさが高く評価されたほか、それを真面目にしっかりした機能のもとで作り込んだことが評価され、「その発想力を今後も活かしてほしい」とのコメントがあった。
吉田さんは受賞コメントで、アイデアを評価されてうれしいと述べ、皆が入浴をできるだけ楽しい気持ちでできるようにしたいと思って開発したと語った。ちなみに、吉田さんは銀賞も同時に受賞しており、そちらを1年かけて作った一方で、この作品は2週間で作ったと明かして笑いをとった。
表彰式後の記者会見によると、吉田さんはプログラミングを始めたのは中学一年生の冬ごろで、ノーコードツールから始めて、中学二年生の秋ごろに本格的にテキストでのプログラミングを始めたという。将来については、プログラミングの道も考えたが、AIが発達してきているので、アイデアや企画に重きを置いた仕事に進みたいとのことだった。ちなみにプログラミングのツールとしてAIを使っているかどうかを聞いたところ、使っているとのことで、特にデバッグで役に立っているとの回答だった。
銀賞4作品
銀賞には4作品が選ばれた。
語学学習のためにフレーズを集める「AI Can」
東京女学院高等学校の菊地桃々さんによる「AI Can」は、語学学習のためにさまざまなフレーズを集めるアプリだ。手で入力するほか、ほかのアプリからも共有で追加できる。AIを使い、さまざまな言語に対応。集めたフレーズは、復習機能により、音声認識で話す練習をし、AIによる添削を受けることもできる。
ヨガのポーズをスマートフォンで判定する「Podge」
広尾学園中学校の藤平真里奈さんによる「Podge」は、ヨガのポーズをスマートフォンでリアルタイムに撮影して、お手本に近いかどうかを判定するアプリだ。ポーズはルーレットでランダムに決まる。動画は保存して後から振り返ることもできる。
同じ趣味の人とのすれ違いアプリとその集計「しゅみーと/みんなの趣味広場」
桜蔭高等学校の椎葉友渚さんによる「しゅみーと/みんなの趣味広場」は、自分の趣味を登録しておいて“すれ違い”により同じ趣味を持つ人やその人のほかの趣味と出会える「しゅみーと」と、その情報を集計して特定の趣味の人が集まりやすい場所がわかる「みんなの趣味広場」の2つからなる。マーケティングへの応用や個人情報保護も考えられている。
銅賞5作品
銅賞には5作品が選ばれた。
自動車事故のときの早急な通報や適切な処置を助ける「NFC for Car」
東京都立八王子北高等学校の鈴木瑠依人さんによる「NFC for Car」は、自動車事故のときの早急な通報や適切な処置を助けるアプリ。車に取り付けたNFCカードにスマートフォンをタッチするだけで自動で119番に通報し、さらに近くの人に助けを求めたり応急処置を調べたりできるという。実際に知人を交通事故で亡くした体験から考えたとのことだった。
ウォーキングのコースを記録して共有する「WalkShare」
学習院女子高等科の加藤心和さんによる「WalkShare」は、ウォーキングのコースを記録して共有するアプリだ。スマートフォン上でウォーキングの目的地を設定し、それを元にウォーキングしたところを記録する。それを元に振り返ったり、友達と共有したり、気に入ったコースを自分のところに保存したりできる。
視覚障害者のための英単語帳アプリ「私たちの単語帳」
東京都立文京盲学校の佐藤心陽さんによる「私たちの単語帳」は、視覚障害者のための英単語帳アプリだ。単語リストや、翻訳、スペル練習、意味練習の機能を持ち、自身を含む弱視でも見やすいように文字の大きさや配色などを工夫した。今後は音声機能も付けていきたいという。
ゲーム感覚で物理を学ぶ「Velocis」
東京都立晴海総合高等学校の笹子悠月さんによる「Velocis」は、ゲーム感覚で高校物理の力学の概念を学ぶアプリだ。講義や、Unityを使ったシミュレーションによる実験、練習問題を「ステージ」としてクリアしていくものだ。













![【Amazon.co.jp限定】1冊ですべて身につくHTML & CSSとWebデザイン入門講座[第2版] (特典:「Webデザイナーのポートフォリオの作り方入門講座」データ配信) 製品画像:2位](https://m.media-amazon.com/images/I/51skMJ-OVcL._SL160_.jpg)