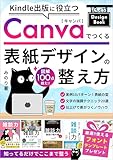やじうまの杜
「/usr」は「User」の略にあらず? Linuxのディレクトリ構造を解説したチャートが話題に
Windowsユーザーも知っておくとWSLを壊さずに済むぞ
2024年6月20日 06:45
「やじうまの杜」では、ニュース・レビューにこだわらない幅広い話題をお伝えします。
Linuxのファイルシステムをわかりやすく解説してくれている画像が、「X」(旧称:Twitter)で話題を呼んでいます。
Linux file system explained.pic.twitter.com/RD7HNOAn6F
— Bytebytego (@bytebytego)June 16, 2024
最近は「Windows Subsystem for Linux」(WSL)などの普及で、Linuxに触れる機会が増えたWindowsユーザーも多いかと思いますが、どのディレクトリ――おおむねフォルダーのことですね――がどんな意味を持っているのかを知らないまま、雰囲気で使っている人も少なくないのではないでしょうか。しかし、ファイルシステムのディレクトリをちょっと知っているだけで、
「/sys は触らないほうがよさそうだな」
「自分のファイルは/homeに置いておこう」
「WSLからWindowsのファイルシステムにアクセスしたいが……/mntあたりにありそうだな」
と見当がつくので、システムをうっかり破壊してしまったり、どこにファイルを置いたのかわからなくなったりといったトラブルを防ぐことができます。
ちなみに、現在のLinuxの「/usr」ディレクトリは「ユーザー」(User)を指すのではなく、「Unix System Resource」の略なのだそうです。どうもUnixができた当初は、「/usr」は「User」のことを指しており、ホームディレクトリも「/usr/<USER_NAME>」にありました。しかし、「/usr」に置くものがだんだん増えてきた結果、ディレクトリが肥大化。同じユーザーのモノであっても、「システムではなくユーザーが使うプログラム」は「/usr」に、ユーザーのデータは「/home」へ置くという運用が一般的になり、「usr」の意味も「User」から「Unix System Resource」の略であるという風に変化していったようです。
まぁ、どっちも間違いとは言えないみたいですが……歴史が長いといろいろあるみたいで、ちょっと面白いですね。













![【Amazon.co.jp限定】1冊ですべて身につくHTML & CSSとWebデザイン入門講座[第2版] (特典:「Webデザイナーのポートフォリオの作り方入門講座」データ配信) 製品画像:2位](https://m.media-amazon.com/images/I/51skMJ-OVcL._SL160_.jpg)