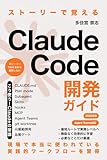Book Watch/鷹野凌のデジタル出版最前線
第6回変化を始めたマンガ家と編集者・出版社の関係 ~デジタル化で変わること・変わらないこと
とり・みき×ヤマザキマリ×佐渡島庸平によるトークイベントより
2018年3月29日 06:45
(株)マンガ新聞は2月26日、マンガ家とり・みき氏とヤマザキマリ氏、クリエイター・エージェンシーの(株)コルク代表取締役社長 佐渡島庸平氏を招き、マンガ家と編集者の関係についてのトークイベントを都内で開催した。本稿では、このイベントの前提になっている5年前の“事件”を振り返りつつ、当時と今とで変わっていないこと、変わっていることを整理しつつ、筆者の考えを述べさせていただく。
発端は2012年、ヤマザキ氏が原作者である実写映画『テルマエ・ロマエ』がヒットしたことに始まる。公開から半年足らずで興行収入59億4000万円を記録。「ヤマザキさんは映画の分配金で大金持ち」と周囲から勘違いされただけでなくその影響は家族にも及び、誤解を払拭するためテレビ番組で「原作料は100万円」と明かし、フジテレビに批判が殺到する騒ぎとなった。
騒動が起きた直後、シカゴに住んでいたヤマザキ氏のもとへ、当時の担当編集者がアポなしで訪問。いきなりプライベート空間へやってきた猪突猛進の彼に対し、イタリア人の夫は激怒してしまう。また、契約のときに、なぜしっかりと条件面を詳細まで吟味していなかったのか、難しいことが書いてあるのならなぜ弁護士に確認してもらわなかったのだと、これまた怒られてしまう。マンガ家という稼業に対する夫の不信感も強くなり、その影響で夫婦仲が険悪になってしまったという。
その上、原作料をテレビで告げた直後、担当編集者から「他局であんなことをして、すぐにフジテレビに謝りなさい」と言われたヤマザキ氏は、それまで自分を守ってくれていたはずの編集者の態度の豹変に戸惑い、悩み続けたあげく一時期「もうマンガ家やめる!」とこぼしていたという。こんな唯一無二の作品が描けるマンガ家をなくしてはいけない! と説得したのが、とり氏だ。当時の詳細な経緯は、2013年9月に日経ビジネスオンラインで連載された、2人へのインタビュー記事“とりマリの「当事者対談」”をご覧いただきたい。
出版社の編集者は、作家側に立つと利益相反になる
「出版社の編集者」は、本来は自社の利益を第一に考えなければならない「社員」なのに、日本では同時に作家のエージェント的役割も担っている。作家側の立場で上司に意見をしたり、映像化でも外部との窓口をしたりと、ある意味利益相反するような、いびつな形になっている。
佐渡島氏によると、社員の立場で会社を説得するのは難しく、作家に泣いてもらうようなケースも多かったという。とり氏も、映像化の話が来て出版社が舞い上がってしまい、作家よりテレビ局を向いてるように感じられ「作家のために動いているのではないのか?」と、裏切られたような気分になったことがあるという。
日本の出版業界はこれまで、義理と人情の世界だった。それゆえいまだに、単行本が出てから契約書が送られてくる、といったことが普通に行われている。担当編集者がろくに説明もせず、いきなり「すぐに持って帰るので契約書のここにハンコ押してください」といったこともあるそうだ。契約書の文言は、作家が読んでもすぐ理解するのは難しい。そのため、契約の文言を吟味するようなこともあまりないという。それでも、それほど大きな問題なく回っているのが現状だ。
逆に、実は編集者側も著作権についてよくわかっておらず、へんな誤解をしているケースもあるそうだ。佐渡島氏曰く、出版社にいても、ともすればなにも知らないまま窓口になってしまうのだ。
また、新人作家が契約書の条項に注文をつけたら、ヘタをすると出版できないかもしれないという恐怖もある。とり氏によると、基本的には最初に提示される契約書には「この作品の映像化権を出版社に委託します」など出版社が多くの権利を確保できる条項が並んでいるそうだ。もちろん作家側から変更の提案はできるのだが、世間知らずの新人の頃はほとんどそのままハンコを押してしまう。連載の存続という生殺与奪の権は出版社が握っているので新人は反論しにくいからだ。逆に、その作家が売れて、あとから「この契約はおかしいのではないか」などと言い出すと、編集側は「オレはあいつにこれだけ手をかけてやったのに、裏切られた」といった気持ちをどうしても抱いてしまうだろうという。
とり氏は理想像として、お金の交渉はエージェントと出版社のライツ担当に任せ、マンガ家は担当編集者と作品のことだけを話し合いたいという。ヤマザキ氏も『テルマエ・ロマエ』騒動が起きた当時、担当編集者に「あなたとはマンガの話だけをしたい。マンガ作りだけをしたい。ほかのことはぜんぶ、弁護士やマネージャーなどほかの人に任せたい」と提案したが、そんな必要は無いし、こちらの提案は信じて任せてもらいたい、という態度を示された。
そういうことを言い出すと嫌がられ、ヘタをすると関係を切られてしまうと、とり氏。テレビ化をめぐる疲労は執筆意欲の減退を招き、結局その出版社を去ることになったが、当時の編集者からは「どの出版社でも仕事はできないからな」などと言われた経験があるという。実際には他社から仕事がたくさん来て、いまでも業界で仕事を続けられているわけだが、新人にそんなことはわからないから言いなりになりがちだ。
逆にマンガ家側も、掲載誌がファミリーみたいな感覚で寄りかかってしまい、あまりに編集者や編集部に依存しすぎているケースも多い。独立した個人事業主らしくない人もいるそうだ。欧米型のドライでシビアな契約関係だと、締切を守れない作家は「契約違反」だとペナルティを科される可能性もある。一概に、日本型の義理と人情の世界が悪いとも言い切れない。
デジタルで売れている作家は、紙でも売れる
実はここまでの論点は、2013年の日経ビジネスオンラインのインタビューでも、あらかた出ていたことだ。5年経った2人の話を聞いても、あまり大きく変わっていない印象がある。佐渡島氏のようなエージェントも現れたが、専門のエージェントはまだ少なく、追いついていないのが現状だ。弁護士も同様だ。
ただ、周囲の状況は大きく変わった。2017年には、コミックス(単行本)の売上が紙と電子で逆転している。マンガ誌売上の激減傾向は止まらないが、出版社も以前よりWebマガジンや無料アプリに力を入れるようになっている。デジタルに対する評価は、作家も出版社も5年前と比べたら大きく変わっていることだろう。
佐渡島氏は、デジタルで売れている作家は紙でも売れるので、数字が見込める作家に対して出版社も期待をかけるという。ヤマザキ氏ととり氏に「いきなりネットで、という手もあるのでは?」と提案するも、ヤマザキ氏は「やっぱり編集者との繋がりが欲しいし」と、とり氏は「移行は必然だと思うが、まだ過渡期で紙の本も好きだし、既存の流通へ乗せるには出版社の力が必要。ヤマザキさんの問題提起の影響もあり、理解のある担当者も増えているので、いまは様子を見ている」という。ヤマザキ氏の「わたしはマンガを作る専門家であって、それを売るのは、売る専門家にお任せしたい」という言葉が印象的だった。
もちろん編集者との相性もあるだろう。人の出会いは運もある。従来は、マンガ家が編集者を選ぶことができなかった。そういう意味で、先日ベータ版がオープンしたばかりの講談社「DAYS NEO」は、作家側が編集担当者を逆指名できるシステムを採用しており、筆者は新しい時代の幕開けを感じている。
鷹野 凌
フリーライターでブロガー。NPO法人日本独立作家同盟 理事長。実践女子短期大学でデジタル出版論とデジタル出版演習を担当。明星大学でデジタル編集論を担当。主な著書は『クリエイターが知っておくべき権利や法律を教わってきました。著作権のことをきちんと知りたい人のための本』(インプレス)。












![【Amazon.co.jp限定】1冊ですべて身につくHTML & CSSとWebデザイン入門講座[第2版] (特典:「Webデザイナーのポートフォリオの作り方入門講座」データ配信) 製品画像:2位](https://m.media-amazon.com/images/I/51skMJ-OVcL._SL160_.jpg)