【第12回】
ユーザーインターフェイス (user interface)
(01/06/27)
窓の杜のソフトライブラリに収録されているオンラインソフトを利用するうえで、ぜひとも知っておきたい用語を解説します。解説内容は窓の杜ソフトライブラリを利用できる範囲とします。
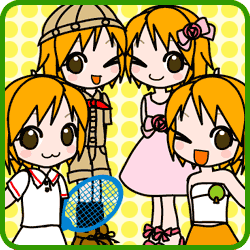 |
ユーザーインターフェイスが変われば
使い勝手も変わる |
パソコンを操作する際に目に見えたり、触れたりする部分を指す。マン・マシン・インターフェイスと呼ばれることもあり、人間とパソコンとの入出力の窓口となる。窓の杜では主にソフトについて用い、ユーザーがソフトを操作するうえで目に見える部分や操作できる部分、つまり“ソフトの見た目”についていう。
Windows上で動作するソフトは、内部では高度な処理過程があり、処理に対する命令も複雑だが、ユーザーはそれらをまったく意識することなくソフトを利用することができる。これはWindowsとWindows上で動作するソフトが、絵のアイコンやボタンで操作対象や処理を選択しながら対話式に操作できるユーザーインターフェイスを採用しているためである。このように操作部分がビジュアルでわかりやすいユーザーインターフェイスをGUI(Graphical User Interface)という。
ユーザーインターフェイスは、ソフトを利用する際にユーザーが直接操作する部分である。ユーザーはソフトを操作しているというより、ユーザーインターフェイスを操作しているともいえるだろう。また、データの入口と出口でもあり、ソフトはユーザーインターフェイスの出来しだいで、使いやすくも使いにくくもなる。たとえばボタンは大きいほうが押しやすいが、そのかわりメニューに並べるボタンの数を減らせざるを得なくなることもある。また、ウィンドウのデザインが美しいソフトは使っていて楽しいが、動作が重くなることもある。
ソフトの使い勝手を左右するため、ユーザーインターフェイスはソフトを選ぶ際にきわめて重要な判断材料となるだろう。入出力が同じでも、ユーザーインターフェイスの違いで操作感はまるで変わってくる。わかりやすくて無駄がなく、操作に無理がないものが一般的にいいユーザーインターフェイスといわれる。ただ、ユーザーの使用状況や環境にも影響されるため、万人にとって完璧といえるユーザーインターフェイスは存在しないだろう。同種のソフトをいくつか試してみて、自分と相性のよいソフトを見つけよう。
(窓の杜編集部/イラスト:石岡 友里)


 トップページへ
トップページへ moridas ~窓の杜使いこなし用語集~ INDEX
moridas ~窓の杜使いこなし用語集~ INDEX