石田賀津男の『酒の肴にPCゲーム』
なぜカテゴリ6Aを選ぶべき? LANケーブルの規格から学ぼう
2025年7月25日 12:02
LANケーブルはカテゴリ6Aでいい! その理由は?
『新しいLANケーブルが欲しいんだけどどれがいい?』と聞かれたら、筆者は『カテゴリ6A』と答える。一般家庭用のLANケーブルは、よほど特殊な事情がない限り、カテゴリ6Aを買えば間違いない。英語表記で「Cat6A」と書かれていることも多い。
筆者に限らず多くの方がそう言うと思うのだが、なぜカテゴリ6Aなのかを聞けば納得すると思う。前回は10Gbpsのインターネット回線について解説したが、LANケーブルの説明を省いていたので、その補足も兼ねて解説をしていきたい。
コネクターは昔から変わっていない
まず、一般的なLANケーブルのコネクターは「RJ45」という名前で呼ばれている。一昔前だと、『電話線のケーブルのコネクターよりちょっと大きいやつ』という説明で通じたのだが、最近は電話線の方を見かけなくなってしまった。
現在、一般家庭で使われているLANケーブルは、ほぼ全てRJ45コネクターを採用している。四角く、8つのピンがあり、抜く時に指で押さえるツメが付いているあの形、と言えばわかるだろう。正式には「8P8C」という別の呼び名があり、RJ45は厳密に言うと仕様が違うのだが、現在はRJ45と呼ぶのが一般的なので、本稿もそれに従う。
コネクターが1種類に統一されているのはわかりやすい反面、規格の違いがわかりづらいという問題がある。例えば1990年代からある10Mbpsの規格である10BASE-Tでは、カテゴリ3のLANケーブルが使われていたが、コネクターは同じRJ45であり、現代のLAN機器にも物理的には接続できる。
もちろん、挿せれば何でもいいわけではない。LANの通信規格に応じたケーブルを使うことが重要だ。
LANケーブルのカテゴリとは何か?
LANケーブルにはカテゴリ○○という名前が付けられている。これが対応する通信規格を示すものだ。基本的にカテゴリの数字が大きいほど高性能、と考えていい。
では、LANケーブルの性能とは何だろうか。現在のLANケーブルにおける性能の違いは、周波数特性の違いだ。
RJ45コネクターのLANケーブルには、ツイストペアケーブルと呼ばれる、中に8本の信号線が通ったものが使われている。この信号線に乗って通信データが運ばれるのだが、通れる周波数の幅が広いほど高性能となる。例えて言えば、道路の幅が広いほど、一度に多くの荷物を運べる、というイメージだ。
ここで具体的なデータを見てみよう。現在主に売られているカテゴリ5eからカテゴリ8までの周波数特性は以下のとおり。
| カテゴリ | 周波数特性 |
|---|---|
| 5e | 100MHz |
| 6 | 250MHz |
| 6A | 500MHz |
| 7 | 600MHz |
| 7A | 1,000MHz |
| 8 | 2,000MHz |
カテゴリの数字が大きくなるほど、周波数特性が広くなっている。
カテゴリと通信規格の関係
ではカテゴリ8のケーブルを使うと通信速度が最も速くなるのかというと、そうはならない。ケーブルはあくまでも物理的仕様であり、通信速度は通信規格によるからだ。
今度は通信規格とLANケーブルのカテゴリの関係性を見ていこう。
| 通信規格 | 通信速度 | カテゴリ |
|---|---|---|
| 1000BASE-T | 1Gbps | 5/5e |
| 2.5GBASE-T | 2.5Gbps | 5e |
| 5GBASE-T | 5Gbps | 5e/6 |
| 10GBASE-T | 10Gbps | 6/6A |
現在、多くの家庭で使われているのは、通信速度1Gbpsの1000BASE-Tだ。LANケーブルはカテゴリ5または5eで対応できる。現在入手可能なLANケーブルはおそらくカテゴリ5eが最下位なので、よほど古いLANケーブルを引っ張り出さない限りは、どんなLANケーブルでも使えると思っていい。
通信速度2.5Gbpsの2.5GBASE-Tは、最近のPCで採用が多い。LANケーブルは実はカテゴリ5eに対応しているため、市販のケーブルならあまり気にせず使える。
通信速度5Gbpsの5GBASE-Tは、最新型のPCの中でも上位機種で時々採用されている。対応するネットワーク機器が少ないため、実力を発揮できる場面は少ない。もし使うとすればカテゴリ6が推奨だが、家庭内で使う程度の距離ならカテゴリ5eでも対応できることが多い。
通信速度10Gbpsの10GBASE-Tは、ハイエンドPCでごくまれに採用がある程度。対応するネットワーク機器は存在するが、まだ高価だ。LANケーブルはカテゴリ6Aで対応できる。またカテゴリ6のLANケーブルでは、仕様上では55mまで通信可能とされており(カテゴリ6Aでは100mまで)、家庭内の利用ならカテゴリ6で問題ない場合がほとんどだと思われる。
さらに上位規格として25GBASE-Tや40GBASE-Tという規格もあるのだが、現時点では一般家庭向けの製品は存在しない。10GBASE-Tの普及もまだまだという現状を考えると、この先も数年程度では状況は変わらないだろう。
通信規格とカテゴリの関係で覚えておきたいのは、どちらか一方が上位規格になっても通信は高速化しないということ。例えば1000BASE-Tの機器にカテゴリ6Aのケーブルを使っても通信速度は1Gbpsのまま。また10GBASE-Tの機器にカテゴリ5eのケーブルをつないだ場合、10Gbpsの通信速度は実現できず、5GBASE-Tより下位の規格での通信になると思われる。
カテゴリ7以上を選ぶとデメリットもある
現状、10GBASE-Tより先の通信規格が一般家庭に降りてくる気配はないので、LANケーブルはカテゴリ6Aを選んでおけば十分ということになる。
しかし、カテゴリ7や8という上位の製品を選んだからといって、通信に不具合が出るというわけではない。より周波数特性が広いケーブルを使用しているのだから、高速化はしないまでも、問題が発生する可能性はまずない。
メーカーによっては、この周波数特性のデータをもとに、『どれを買うか迷ったら、上位のカテゴリの製品を買おう』と呼びかけていることもある。安定した接続という点で考えればそれでいいのだが、実はデメリットや問題も抱えている。
デメリットとしては、まず価格が上がる。カテゴリが上位の製品は高性能である分、生産コストが上がるという当然の話だ。
次に、ケーブルが硬いこと。上位カテゴリになるほど、信号線が太くなったり、さまざまな電子機器から発せられる電磁波ノイズを防ぐためのシールドが導入されたりして、ケーブルは太く、硬くなっていく。性能が上がる代わりに、ケーブルは曲がりにくくなり、取り回しが悪くなる。
シールドについては、LANケーブルではシールドがあるものを「STP」、ないものを「UTP」と呼んで区別している。ただSTPはアースを適切に処理しないとあまり意味がなく、また一般家庭でそこまでノイズ耐性が求められることは滅多にない。余計な問題を生まないために、UTPを使う方が無難だ。
問題となるのはカテゴリ7以上の製品だ。カテゴリ7以上の規格ではSTPが必須となっているので、UTPを選ぶ前提ならカテゴリ7以上は選択肢に入れられない。
さらにカテゴリ7、および7Aは、RJ45のコネクターを採用した規格が存在しない。一般的に売られているカテゴリ7/7AのLANケーブルは、600MHzや1,000MHzの周波数特性を持つ高品質LANケーブルであるものの、カテゴリ7/7Aの製品としては規格外になる。逆にコネクターがRJ45ではない、規格にのっとったカテゴリ7の製品も見かけない。コネクターがRJ45なら、規格上はカテゴリ6AのSTPケーブルと見る方がよい。
カテゴリ8のLANケーブルについては、RJ45のコネクターを採用したカテゴリ8.1が規格化されている。40Gbpsの40GBASE-Tに対応するものだが、現時点では一般家庭用の製品ではない。RJ45を採用したLANケーブルの中では最も周波数特性が広いことは事実だが、オーバースペックで扱いづらく、高価な製品になる。
新たに買うならカテゴリ6A。古いケーブルの劣化にも注意
以上の理由から、カテゴリ7以上のLANケーブルはおすすめしない。現時点で一般家庭向けに最も扱いやすく、高性能なLANケーブルは、カテゴリ6Aだと言える。
カテゴリ6やカテゴリ5eの製品もまだ売られてはいるが、カテゴリ6Aのケーブルとの価格差は僅かであることが多い。ケーブルの柔らかさなど、取り回しの面では下位カテゴリの方が有利なはずだが、カテゴリ6Aの製品はかなり幅広く売られており、細いケーブルやフラットケーブルなども多数存在する。
こういう話をすると、『細いケーブルやフラットケーブルは規格に準拠していない!』という声も聞かれる。そういう製品があるのも確かで、誤解を恐れず言えば、『カテゴリ6Aに相当する性能だとメーカーがうたっている製品』である。
しかし、法的な問題があるような話ではない。細いケーブルも、フラットケーブルも、あれば便利な製品だ。ただし、信頼できるメーカーの製品を選ぶことは重要だ。仮に規格で求められる性能が出ていなければ、不良品として交換を求められるくらいの安心感は欲しい。LANケーブルも工業製品である以上、品質のばらつきや初期不良はあり得る。
通信規格を満たすケーブルであったとしても、安心はできない。ケーブルの抜き差しによってピンが傷むことは意外とよくあるし、経年劣化による断線、汚れの付着などもあり得る。通信速度が遅いなと感じた時には、PCやルーターのリンク速度を確認してみるといい。筆者も過去に1000BASE-Tで接続していたPCが、普段は1Gbpsでリンクするのに、時々100Mbpsになっていた経験がある。LANケーブルを交換すると正常に戻った。
『カテゴリ5e以下のケーブルは捨てろ』という声も聞くが、規格上は2.5GBASE-Tでも十分使えるので、無理に捨てる必要はない。ただ古くなっていることが多いと思われるので、問題ないかどうか確認しておく方がいい。特にツメが折れているものは勝手に抜ける原因になるので、なるべく早く交換しよう。最近はツメが折れにくいLANケーブルが多く売られている。
壁内配線など長距離で引くケーブルは、なるべく長期にわたり交換しないで済むようにしたいが、これも今ならカテゴリ6Aでいいと思う。交換が必要になるのは、10GBASE-T以降の規格でカテゴリ6Aが使えなくなる時なので、おそらくこの先20年は使えるだろう。それ以上のものが必要になる時には、現状では存在しないケーブルを求められるか、全て無線に変わっているのではないかとも思う。
ということで、『LANケーブルはカテゴリ6Aを買おう』という話は以上だ。余談だが、昔はPCのLANポートを直結して通信するためのクロスケーブルもよく売られていた。クロスケーブルとは、LANケーブルの内部の信号線を一部入れ替えることで、互いの送受信を適切に行えるようにしたものだ。
しかし現在は「AutoMDI/MDI-X」という機能で、接続されたケーブルがストレートかクロスかを判別し、適切に通信できるようLANポート側が調整してくれる。これによりクロスケーブルは事実上不要になり、店頭でもあまり見かけなくなった。
1977年生まれ、滋賀県出身
ゲーム専門誌『GAME Watch』(インプレス)の記者を経てフリージャーナリスト。ゲーム等のエンターテイメントと、PC・スマホ・ネットワーク等のIT系にまたがる分野を中心に幅広く執筆中。1990年代からのオンラインゲーマー。窓の杜では連載『初月100円! オススメGame Pass作品』、『週末ゲーム』などを執筆。
・著者Webサイト:https://ougi.net/
PCゲームに関する話題を、窓の杜らしくソフトウェアと絡め、コラム形式でお届けする連載「石田賀津男の『酒の肴にPCゲーム』」。PCゲームファンはもちろん、普段ゲームを遊ばない方も歓迎の気楽な読み物です。

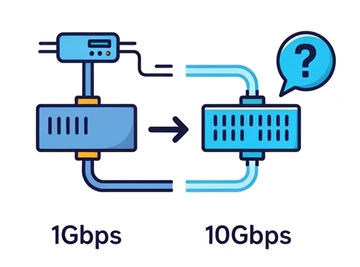

















![【Amazon.co.jp限定】1冊ですべて身につくHTML & CSSとWebデザイン入門講座[第2版] (特典:「Webデザイナーのポートフォリオの作り方入門講座」データ配信) 製品画像:2位](https://m.media-amazon.com/images/I/51skMJ-OVcL._SL160_.jpg)







