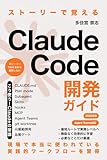生成AIストリーム
ChatGPT“ジブリ化”で問われている生成AI時代の著作権(2) 先進的すぎて伝わらない、日本の著作権
2025年5月28日 16:58
連載「生成AIストリーム」、AICUのしらいはかせ(X:@o_ob)です。
前回はChatGPTによるジブリ化の現象とその経済効果に関する考察をしました。今回はそこから発生する著作権的問題を考えてみたいと思います。
「日本だけが日本の著作権を気にしている」
日本では、2023年5月に行なわれたG7広島サミットで、国や分野を超えてますます顕著になってきた生成 AI の課題について評価する必要性が認識され、文化庁が「AIと著作権に関する考え方について」というテーマで文化審議会著作権分科会でディスカッションが行われていました。
2024年3月15日には、法制度小委員会による言及が「公的文書」で明確になりました。
日本の文化庁が「依拠性」と「類似性」の二段階基準を明確に対外発信したのは、これが初めてです。Gemini 2.5 Deep Researchによると文化庁が著作権侵害の成立に類似性と依拠性の双方が必要であると明確に宣言していると特定できる最古の公式文書は、令和5年(2023年)7月付の「AIと著作権に関する考え方について(素案)」及び同年12月付(令和6年3月15日更新情報あり)の「AIと著作権に関する考え方について」で、これらの比較的新しい文書が、類似性・依拠性の原則自体は判例法理において「長らく確立されてきたものである」という前提に立脚しています。
これは生成AI時代において、著作権侵害の判断を明確化する上で重要な指針であり、国内の議論に影響を与える資料となりました。一方では、この方針は日本語のみで、国内の著作権理解に熱心な賢い方々だけに理解されている、というのが現状のようです。この連載でもパブリックコメントの実施などを紹介してきましたが、AI時代におけるクリエイター視点、特に世界のプレイヤーに対応できる新しい著作権の枠組みといった議論や、議員立法といった流れには至りませんでした。
- ⇨「デルタもん」を生成しながらAIと著作権の未来を考える
- https://forest.watch.impress.co.jp/docs/serial/aistream/1568559.html
著作権は産業やメディア技術の進化とともに見直され、比較的高頻度に行われているのです。近年の事例だと、映画の盗撮の防止に関する法律が、議員立法により第166回国会において成立し、平成19年5月30日に平成19年法律第65号として公布され、平成19年8月30日から施行されました。
では、諸外国ではAIと著作権の関連はどう定義されているでしょうか? 先日、サンフランシスコの生成AIによる国際映画祭「Odyssey」の授賞式のセレモニーで、とあるアニメ風の画像が出せることを特徴としている画像生成AIモデルのスタートアップ企業の幹部とディスカッションする機会がありました。何というモデルかは伏せておきますが「ドラゴンボール」とか「孫悟空」とか「ピカチュウ」とプロンプトに打てば、そのキャラクターが生成されるような画像生成AIを想像してください。そこで、彼から『日本だけが“その著作権”を気にしている』といわれてしまいました。
- ⇨Project Odyssey - Season 2 データで見る、AI動画生成の現在。
- https://note.com/aicu/n/n1ba689175e77
確かに日本の弁護士でも、商標やキャラクター名称に依拠した画像を生成するサービスについては若干意見にブレがあります。そこでちょっと調べてみました。以下が、日本・中国・米国におけるAI無断学習、依拠性、類似性に関する法的整理です。
日本
- 無断AI学習「合法」 著作権法第30条の4により、情報解析目的であれば無断利用可能
- 依拠性「推定可能」出典や類似性を元に依拠があったと判断されることがある
- 類似性「侵害となる可能性あり」表現が類似し、依拠があれば著作権侵害として扱われる
中国
- 無断AI学習「定義なし(グレー)」明確な条文はなく、状況次第で違法とされる可能性あり
- 依拠性「明文化なし(判例ベース)」裁判所が依拠を認定した事例は存在
- 類似性「近似で違法判定あり」視覚的に似ていれば侵害とされた判例あり
米国
- 無断AI学習「フェアユース(条件付き合法)」用途、変容性、収益影響などを総合的に判断
- 依拠性「コモンロー(判例)による判断」意図・使用量・アクセス可能性などを含めた総合判断
- 類似性「酷似+変容性低ければ違法の可能性あり」特に商用で明確に元ネタが想起される場合は厳しくなる
AI学習については「日本は圧倒的に緩やか」であり、本日2025年5月28日には「人工知能関連技術の研究開発及び活用の推進に関する法律」が参院本会議で与野党の賛成多数により可決、成立したところです。著作権法第30条の4は、著作物を「著作物に表現された思想又は感情の享受を目的としない」場合、その必要と認められる限度において利用できるとしており、G7では日本だけがAI無断学習を特例として許可している状態です。無断学習と類似性については米国や中国の方が厳しい、というのが現状で、『日本だけが日本の著作権を主張している』と言われる要素の1つがここにあります。さらに米国の場合はフェアユース、例えば研究目的など、公共性などが総合的に評価される上に「コモンロー」、つまり判例が全てです。この場合は立法よりも司法の方が強い可能性があるのです。
このあたりは、Gemini 2.5 Pro「Deep Research」を使うと、法律の条文ベースで各国の状況をあっという間にエビデンス付きで調査してくれます。例えば、日本と同様の例外規定は. シンガポールにあります。
日本では文化庁が依拠性と類似性を明確に切り分けた議論を2024年~2025年に行っている点が特徴的で、各国に浸透しているとは言い難いです。ここが「日本だけが日本の著作権を気にしている」と言われる2つ目の点です。
日本も米国においても著作権法では「スタイル」は保護されない、つまり「絵のタッチ」や「作風」「構図傾向」などはアイデア(Idea)として扱われ、保護対象とはなりません。このため、ジブリ風、ピクサー風といったスタイル模倣そのものは著作権侵害とみなされません。
AIが生成された生成物が「実質的に類似(Substantial Similarity)」とされると、米国の判例法では、AI生成画像が既存の著作物と“実質的に似ている”かどうかが問われます。一方で、Image-to-Image (i2i)のアップロード時の複製権、公衆送信権、肖像権などもあります。 文化庁が2023年7月に公表した「AIと著作権に関する論点整理」では、「Image to Image (i2i)」を名指しで挙げ、既存の著作物を入力して類似のものを生成させる行為は、依拠性が認められる可能性が高い例として示しています。LoRAについても、特定の画風を学習させる目的が「享受目的」にあたる可能性などが議論されており、文化庁がこれらの技術動向に無関心ということはありません。
さらに米国の著作権においては、フェアユース(Fair Use)という概念がとても強力です。フェアユースは、著作権者からの許可なく著作物を利用できる例外的なケースを指し、商業的な目的よりも、非営利的で批評、教育、研究などの目的での利用が認められやすい傾向があります。クリエイティブ・コモンズのようなライセンスが整備されており、公共で利用する教科書などの著作権解決方法として有用です。例えば楽曲生成AI「Stable Audio」にはクリエイティブ・コモンズのデータで学習されたモデルも存在します。
なお、日本では「商用利用」という概念に明確な定義がありません。例えば、クリエイティブ・コモンズには「CC BY-NC-ND」(Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs)「表示-非営利-改変禁止」という定義があり、作品を複製、頒布、展示、実演を行うにあたり、著作権者の表示を要求し、非営利目的での利用に限定し、いかなる改変も禁止することができます。
営利か非営利か、という定義をはっきりさせることで、利用許諾のライン引きは明確になる面があります。例えば、この分野の話では著作権の「財産権」が最も強力な権利を持つことは間違いないのですが、その財産権をベースに商標権による保護や解決も模索されています。特定の製品やサービスを識別するために、視覚的に認識される特徴全体を保護するトレードドレス(Trade Dress)やミスリーディング表示(False Designation of Origin)などの領域にも関係しています。最近では経産省が意匠法、商標法、不正競争防止法の視点から声優の声の無断利用についての見解を発表しています。偽物が演じることで「周知表示混同惹起行為」や、他社のブランドを自社商品に使用する「著名表示冒用行為」に該当する、という見解です。
- ⇨声優のAI音声、無断利用に警鐘 経産省、違反の恐れを例示 - ライブドアニュース
- https://news.livedoor.com/article/detail/28724117/
- ⇨前回までにいただいた御指摘事項等に係る対応について
- https://www.meti.go.jp/shingikai/sankoshin/chiteki_zaisan/fusei_kyoso/pdf/028_04_00.pdf
件の米国AI企業幹部からは『ChatGPTのジブリ化(Ghiblification)以降、我々はあの品質を超えることを目標にしている』、『日本からも我々のモデルを使っている人が多くいる、そのデータはしっかりと押さえている』、『日本だけが日本の著作権を気にしている』と言われてしまいました。つまり、違法ではなく経済的な価値があるのだから、全力で活用するということです。まさにその通りで、「ジブリ風」だけでなく、ドラゴンボールやガンダムといったIPのニュアンスの再現は、実効的に経済的な価値を持っています。
OpenAIの研究責任者が「ジブリ風画像」を公に投稿・活用した事例は、生成AIの出力が文化的IPに接近し、著作権・商標・パブリシティの境界を曖昧にしつつある現状を象徴しています。
IMAX版「もののけ姫」の売り上げにもあるように、依拠も経済的効果もあることは明確なのです。
もちろん『ChatGPTでジブリ化画像のタイムラインを眺めていたからIMAXを観に行きたくなった』という視点もあるでしょうし、逆に『ChatGPTで特定の画風を流行らせれば、それ自身が広告プロモーションになるのでは』と考える人もいるでしょう。しかし、ChatGPT上では「コンテンツポリシー」が設定され、ジブリ風が生成できなくなった瞬間もありました。何を制限し、何を表現可能にするかはOpenAIのコンテンツポリシーのみ決まる、というのはちょっとおかしい話で、ComfyUIを中心としたオープンソースのモデルやUIはそのような自由を担保するためにも大事な活動です。
日本の著作権は、先進的な法律で、各国の法改正がこの後、追従してきた時に、どのような状態になるかを意識して、自国の資産を防衛していかねばならないフェーズに入ると考えていいでしょう。
次回は「著作権の“神殺し” – CC神のNCをめぐる仁義なき戦い」をお送りします。















![【Amazon.co.jp限定】1冊ですべて身につくHTML & CSSとWebデザイン入門講座[第2版] (特典:「Webデザイナーのポートフォリオの作り方入門講座」データ配信) 製品画像:2位](https://m.media-amazon.com/images/I/51skMJ-OVcL._SL160_.jpg)