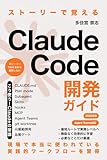石田賀津男の『酒の肴にPCゲーム』
「シヴィライゼーション」シリーズ最新作「Civ7」発売! ……の前に「Civ6」を遊んでみた
今からでも十分楽しい、文明進化を競うターン制ストラテジーゲーム
2025年2月6日 16:31
あえて前作から遊んでみよう
対戦型ストラテジーゲーム「シヴィライゼーション」シリーズの最新作、「シドマイヤーズ シヴィライゼーション VII(Civ7)」が2月12日に発売される。コンテンツが追加された「デラックスエディション」または「創始者エディション」を購入すれば、2月6日からプレイ可能だ。
本シリーズはターン制のシミュレーションゲームとなっており、世界中からさまざまな時代の指導者が集い、世界の覇権をかけて争う。ファンの熱中度が極めて高い作品としても知られ、新作が発売されるたびに『睡眠時間がなくなる』とか『止め時がない』という喜びの声が聞こえてくる。
ただ筆者とはどうも縁がなく、2016年発売の前作「シドマイヤーズ シヴィライゼーション VI(Civ6)」はベンチマークで使っただけでほぼ放置していた。せっかくの機会なので、新作が出る前に遊んでみようかと思う。
「Civ6」には追加コンテンツがいくつも用意されており、本体を含めてすべて購入すると2万円を超える。ただ発売から時間が経過したこともあり、昨年末には全部入りのバンドル版「Sid Meier’s Civilization VI Anthology」が92%OFFの1,841円でセールになった(2月4日時点では52%OFFの11,477円)。シリーズの導入体験として、あえて新作ではなくこちらから遊んでみるのもいいと思う。
文明を進化させ、各々の勝利条件を目指す
筆者が本作について知っている知識といえば、非暴力・不服従の理念で知られるインドの指導者「マハトマ・ガンジー」が、突如発狂して核戦争狂になるバグの話くらい。この話はデマだそうだが。
本作はターンベースのストラテジーという独特なシステムを採用している。覚えることが多く、導入部分は難しいのだが、そこをカバーする丁寧なチュートリアルが用意されているので安心だ。
最初にプレイヤーの分身となる指導者を選ぶ。指導者によって能力が異なるが、チュートリアルでは「クレオパトラ」と「ギルガメシュ」の2択なので好みで選ぼう。
ゲームはヘックス(六角形)マップ上で展開される。ゲームの流れとしては、まず初期ユニットの「開拓者」で好みの場所に都市を建設。周辺にある食料や資源をもとに都市の人口を増やし、戦士や斥候といったユニットを作成する。
マップは最初、都市の周辺しか見えない状態だが、ユニットを動かしていくことでより遠くを探索し、地図で見える範囲を広げていく。その先で、他の指導者による文明と遭遇したら、仲良くするのか敵対するのかを考えつつ、誰より早く勝利条件の達成を目指して文明を発展させていく。
文明の発展には、技術と社会制度の研究が必要になる。技術は新たな兵器や資源獲得に必要なもの、社会制度は法律や外交、軍機、宗教などが含まれる。いずれもツリー状の研究進行表があり、何ターンかかけて研究することで獲得できる。
……まだまだ遊び方の説明はあるのだが、本作において重要なのは勝利条件の理解だ。軍事ユニットを作成し、他の文明と戦って滅ぼせば勝利となるのはイメージがわくと思うが、本作にはそれ以外にも勝利する方法がある。
具体的には、自文明の宗教を他国に浸透させる、科学を発展させ地球外に進出する、文化を進展させ多くの観光客を呼ぶ、外交的支持を集める、という方法がある。いずれも特定条件を最初に満たした文明が勝利となる。
ある指導者は戦闘で勝利しようと他文明を攻めるが、別の文明はひそかに宗教を広め、また別の文明は科学研究に注力している……といったような形で、それぞれの思惑で駆け引きが生まれてくる。
純粋な戦略の駆け引きで競う
チュートリアルでは、戦闘によって他文明を滅ぼす目標が設定される。軍事ユニットを作成して、他文明の首都を制圧したら終了だ。ただし、それまでには長いターンを費やして技術と社会制度を研究しつつ、どこの文明にも属さない蛮族とも戦わねばならない。
やることは多いのだが、ターンごとに各都市、各ユニット、各研究でできることは1つずつと決まっている。都市でのユニット等の生産や、研究の進行には、数ターン以上の時間がかかるので、一度設定すればしばらくは触る必要がない。またユニットも1ターンでの移動距離が限られているため、目的地が遠いほど到着に必要なターン数が増える。
今やるべきことが明確ならば、指示を出してしまえば数ターンは触る必要がない場面も多い。未操作のものがあれば指示を求められるので、動かし忘れるということもない。最初は覚えることが多くて手間取るが、流れがわかってしまえばプレイに困ることはない。
しかし、ここからが本作の難しいところ。限られたリソースをどのように振り分け、何を目的にしてどのように研究を進めていくか。これを決めて適切に指示するのが実に悩ましい。敵からの攻撃を恐れて軍事ユニットを揃えても、敵が来なければ研究が遅れるだけ。逆に都市を拡張して人口を増やすことを優先したら、今度は敵がやってきた……ということもある。
そしてこれこそが本作の面白さだ。いかに他文明を出し抜いて勝利条件を達成するか。他国の情報を得るには実際にユニットを近くに送らないといけないし、目に見えない情報もいっぱいある。どうすれば勝てると決まった道筋はなく、文明ごとに得手不得手もあり、いろんなやりようがある。
ゲームとしては、ボードゲームをベースにしながらも、デジタルでしか実現できない仕組みを導入して遊びやすさと面白さを生んでいる。オンラインで他のプレイヤーと対戦できるというのも、ボードゲームファンなどに受け入れられているのだろうと思う。
ゲームの手ごたえとしては、リアルタイムストラテジー(RTS)の「Age of Empires」シリーズによく似ている。本作はターンベースではあるが、文明を古代から進化させながら、複数の勝利条件を目指すという考え方は共通している。RTSではないので素早い操作を求められず、純粋に戦略性を競う内容なので、むしろ年配のプレイヤーの方が楽しめるのではないかと思う。
筆者はシミュレーションゲームが致命的に下手で、チュートリアルすらクリアできないでいるが、これはチュートリアルに限ってセーブができず、数時間まとまったプレイ時間が取れないのも理由だ。ゲームの理屈を理解したら、通常のシングルプレイモードで遊ぶといいと思う。
筆者がCPUに勝ち、誰かと対戦できるようになるまでにはまだまだ長い時間がかかりそうだ。それでも文明の勝利を目指して心躍る感覚は確かにある。発売から8年以上が経過した作品だが、今遊んでも何ら古臭さはない。新作は高価で初心者が手を出しづらいと思うが、セールで安価になった本作からシリーズの面白さを体験してみるのもいい手だ。
最後にもう1つ。筆者は本作のゲーム内容も気に入ったが、一番気に入ったのはタイトル画面で流れるテーマ曲「Sogno di Volare」だ。今後はこの曲を聞くだけでテンションが上がると思うが、どうやら本作のために作られた曲らしい。今後は使われないとしたら、何とももったいない……。
1977年生まれ、滋賀県出身
ゲーム専門誌『GAME Watch』(インプレス)の記者を経てフリージャーナリスト。ゲーム等のエンターテイメントと、PC・スマホ・ネットワーク等のIT系にまたがる分野を中心に幅広く執筆中。1990年代からのオンラインゲーマー。窓の杜では連載『初月100円! オススメGame Pass作品』、『週末ゲーム』などを執筆。
・著者Webサイト:https://ougi.net/
PCゲームに関する話題を、窓の杜らしくソフトウェアと絡め、コラム形式でお届けする連載「石田賀津男の『酒の肴にPCゲーム』」。PCゲームファンはもちろん、普段ゲームを遊ばない方も歓迎の気楽な読み物です。
























![【Amazon.co.jp限定】1冊ですべて身につくHTML & CSSとWebデザイン入門講座[第2版] (特典:「Webデザイナーのポートフォリオの作り方入門講座」データ配信) 製品画像:2位](https://m.media-amazon.com/images/I/51skMJ-OVcL._SL160_.jpg)